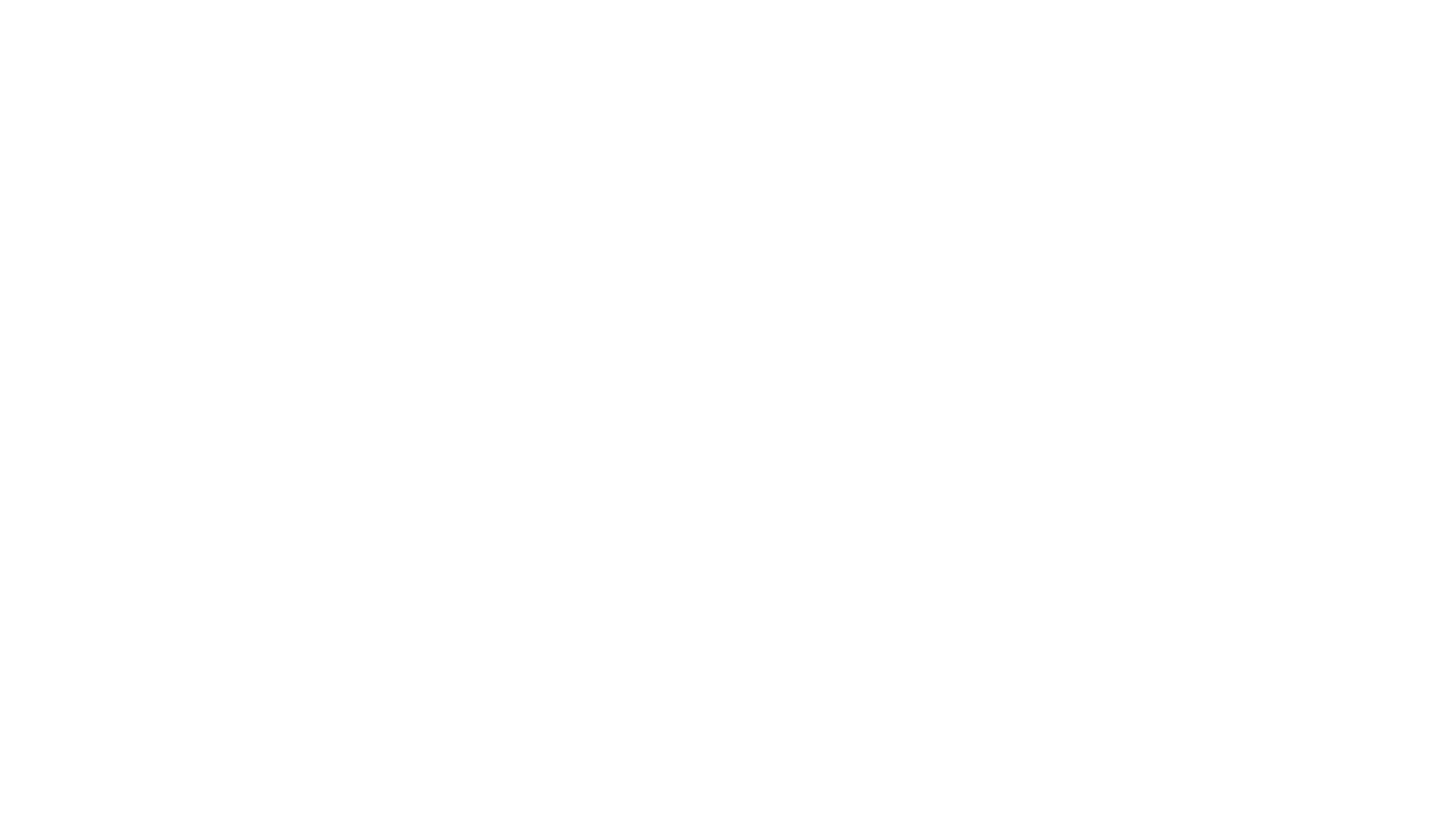2017年4月29日。
この日、東京は異様な空気に包まれていた。
にっこりとした快晴の青空がじっとりと温い雨を降らせ、傘を持たない人々の頭上目掛けて飛び回る。
晴れては降ってを繰り返し、小走りで街を行く大人たちをからかっているかの様に。
大勢を巻き込んだこの不快感が大気をも利用した「彼ら」の演出であること、また今宵執行される奇妙なミュージカルの前兆であったことを我々はまだ知る由もなかった。
東京恵比寿はLIQUIDROOM。
なんとも湿っぽい名前をした会場だが、俗世間からあぶれた変わり者たち(仮にウェンディとする)が雨宿りをするにはもってこいな偏屈さだ。
外界より一足早く暗転した会場にそれまで咲いていた談笑の声は消え、フロア中に格式高いクラシックが響き渡る。
幕間から差し込む真っ青な光がフロアへ差し込めば、いつの間にか姿を現していたひとつの人影がこちらの存在に気付き、ゆっくりと腰をあげた。
物々しい雰囲気に凍りつく観衆。おぼつかない足取りで一歩、また一歩とこちらへ近付くその人物は恨めしそうに我々を指さし、人体から発しているとは思えぬ低く濁った声で歓迎とも威嚇ともとれるうわ言を吐く。
真っ赤に汚れた口角をヒクッと持ち上げ不敵な笑みを浮かべる彼を背後から殴りつける強烈なライト。
微動だにしない観衆に一切の慈愛を捨て、奴は先手『アルトラブラック』で我々を早々に殺しにかかるのだ。
犬歯をも一瞬で砕くドリルの様な3倍速ギターに目が回りそうになった頃、久我新悟のような成りをした例の男がおどけたポーズで「ハイハイゼア」と陽気に狂ったご挨拶。
その瞬間、そこに在るすべてのヒト・モノ・ココロが一斉に破裂する爆音が会場中にこだました。
たかぶる興奮を抑えきれず、靴底にバネでもつけてんのかしら?と思わされるほどに絶えず舞台を跳ねまわるアルトラフリーク。
「暴力」をテーマとした本作に相応しく、歌い出しド頭で歌詞をぶっトバしてしまうあたりに若干の久我新悟感が見受けられたが、おそらく別人だろう。
フロアを見渡せば先程までの戦慄が嘘だったかのよう、観衆一人ひとりがステージ上で幼児性を露わにしている彼に共鳴し始めているではないか。恐るべし順応型ウェンディ。
互いの狂暴性に油を注ぎ合う様はまっるでギャングエッイッガ!
過去に育まれてきた楽曲のキャストを片っ端から暴徒化させてしまうこの空気感を引きずったまま繰り出された『サイド・リブラの場合』。
ここに登場する悲劇のアクター「サイド」もまた例に漏れず、実に冷酷な人格へと変貌を遂げていた。
この日のステージで脚光を浴びていたのは、ショウを切断しアニメとなったサイドの姿。
理性と体温を失った彼を止められる者など、三次元のこの世界には存在しない。
手の届かない距離にあっても、自らの歌声でその場にいるすべての人間を一斉に殴りつける術を手に入れた久我新悟似の男が魅せる高刺激なパフォーマンスに怖気づき、「こいつはヤバい…」と右へ右へ目線を逃がせば、そこには身体に電流を流されたかの如く激しい痙攣を繰り返し、完全にイキきった目つきでギターを搔きむしる男の姿が。
会場を飲み込まんばかりに大きく開いたその口に更なる媚薬を注いだのは『ウロボロス』。
蛇に見立てた右腕をウネウネさせるファンキーなアクションで観衆の頬を緩ませ油断させた後!ブレイクのタイミングで発狂スイッチ!オン!
その先の彼はもはや「ギタリスト」ではなく、「人格を持った暴れん坊ギターにしがみつく男」と化していた。
人体とギター。そのどちらが本体なのかを曖昧にさせる一心不乱無我夢中なプレイたるや、体のどっかしらのパーツが外れてしまうんじゃないかと心配になるほどだ。
「真っ当な人間が見たい!」と、今度は目線を下手側へ逃がす。
すると、そこには地に額がつくほど身体を大きく折り曲げた長身長髪の艶やかな殺し屋が。「音の出る家具」といっても差し支えない超重量のビッグベースを豪快に弾き倒す姿は歩く現代アートともいえよう。
唯一の良心に思えたドラマーに助けを求めようにも、彼もまたそのすべてに触発され、我々になど構っている余裕はなさそうだ。
どこを観ても「普通」にはありつけない異常な空間で溺愛の暴力にされるがまま、覚えのない快感と踊り狂う観衆。
「こういうのが好きなんでしょ?」という生温い確認作業とはまるで無縁。
「君はこんなものにも興奮を覚える生き物なんだ」と、知られざる真実を自信満々に説く彼ら&それを真っ向から受け止める観衆との関係性に一種の「教育」を見た気がした。無論、義務ではない超任意の。
あの場に居合わせた誰もが今でも鮮明に思い出せるであろう『この密室よりくちづけを』の演出も実に見事であった。
妖艶なピンク・パープルのライトを背に、内ポケットから煙草を取り出すセンターの男。
彼が優雅に煙を吐く際の呼吸音「フゥー」、勢いよく吸い込んだ主流煙を喉に絡ませ咳き込む声「ゴホッゴホッ」、それを誤魔化すかの様に繰り出したハンドクラップの音「パンパンッ」、かかとで陽気に床をタップする低音「ズンズンッ」、これらひとつひとつのアクションに伴う些細な動作音がリアルタイムでサンプリングされ、それが延々ループし、徐々にリズムを生んでいく。
やがてすべてのサウンドがひとつに重なり合い、サッと音が止んだ瞬間、マイク伝い、男性客を除く数百人の女性へ一斉に声で口づける彼の囁きはさながらピンクなR18ムゥビィ。
モザイク必須なイケない一幕に乙女は深く酔いしれたことだろう。
密室での情事に発生した致死量のエロスがリキッドルームを液状化させた歴史的瞬間であった。
そして、ここからが本コンセプチュアル公演のメインディッシュともいえるコアでマニアックかつディーーープなお時間。
唇のみならず心をも塞がれ、シーンと静まり返った空間に響いたのは…も、木魚?
観衆の頭上に大きな「?」が浮かび、喜怒哀楽のどれにも該当しないおかしな感情に右往左往していると、なにやら聴き覚えのある言葉が耳をくすぐった。
タトエバミチノミチバッタリアアミギミタリヒダリミタリ…
そこで初めてこの唄が『不条理、痛快、蛇の歌意』であることを知る。
彼らがアレンジ魔人であることなど、ここにいる誰もが承知の事だが、ここまでくると原曲との相違点云々どころの騒ぎじゃなく、もはや「歌」なのかどうかさえも怪しまれるレベル。
あの饒舌な鬱屈垂れ流しナンバーがリズムを失った途端、あれよあれよとハードな御経に大変身。
どうやら「教育」→「官能」ときて、舞台は「宗教」へと大きく転換したようだ。
『飽聴のデリカテッセン』では、黒いテーブルが久我新悟と思しき男の目前にチェックイン。それも真っ赤な林檎のおまけ付き。
レトロなリズムに合わせ、手元の包丁で器用に皮を剥きながら歌う彼の声に和むフロア。
人懐こい音色にのせられた皮肉100%の御唄に舌鼓を打てば、ここで悪夢の不意打ち『大計画』。
人格スイッチが再び「凶」に入った久我新悟らしき男の表情は最後列から観てもおぞましいものがあり、先程まであんなに愛でていた真っ赤な果実をナイフで幾度も突き刺す始末。
神経を経由した悦楽に飽きた彼は、脳で直接的に感じる快感に溺れてゆく。
ときに赤い皮が女性の服に見えたり、真っ赤な果実が人の心臓に、心に見えたりと。音楽のアレンジに留まらず、ひとつの物体に向けられる表情や所作の違いによって、意思を持たない「モノ」自体に様々な想像を掻き立たせる演出は、彼らが紛れもない「表現者」であることを証明した。
そう、言わばこの日のライヴはLIPHLICH監修によるLIPHLICH不在のショー。
自らを理想のキャラクターに仕立て上げ、舞台上で自らを解体するという、意識を振り切り過ぎれば自我をも失いかねない非常に危険な催しなのだ。
それを娯楽として体現し、我々の感情を思うがままに操ってしまう彼らの生き方に勇ましさと同等の儚さを感じずにはいられない。
絵画の様、微動だにせずステージに釘付けになっているウェンディの姿は、自己に陶酔しきっている彼らの目にどう映っているのか。機会があれば是非とも聞いてみたいものである。
続く『It’s a good day to anger』では、ウェンディの体内に沈殿していた「動」のフラストレーションがマッテマシタアアアア!と声をあげ、今日一番の怒号がステージへ放射された。
互いを求める爆発的な声と声とで正々堂々殴り合う様は実に単純明快で鮮やかだ。
場面はそのまま『HURRAH HURRAY』へと流れ、「これは釣った魚に次から次へと餌をやる戦法か」と心躍った浅はかな我々を嘲笑うかの様に『時に夢想者は』をお見舞い。再びダークサイドへと観衆を引きずり込んでいく。
用意した全ての落とし穴に我々を沈めていく彼らの策略が秀逸であるのはもちろんのこと、どんなに過度な緩急にも食らいつき集中力を切らさず、4人から成るすべてを一滴もこぼさず受け止めようとするウェンディの真摯な姿には「ファン」という概念を超えた何か大きなものを感じさせられる。
LIPHLICHの芸術における一瞬の斑、些細な感情の推移をここまで高純度で感じ取れる理由のひとつは、彼女たちの敬意から生まれる純粋な環境作りのおかげであることに間違いはないだろう。
優美に響き渡る憂いのファルセットと静かに激しく感情を揺さぶる3つの音色。
この澄み切った静寂の中でこそ最大限の輝きを放つバラードと、この日、この会場で、この人たちと出逢えたことを心から感謝したくなるような素晴らしい時間がそこには流れていた。
繰り返される「You are Veautiful」の声がその美しい静寂を賞賛しているかの様にも思え、うっとり余韻に浸ろうとするも無惨。
またしてもギアをトップに入れた彼らからブン投げられた冥土の土産三選『Give me Chill me Killing me』『バナナ・スキンヘッド』『MANIC PIXIE』を前に天井を突き破るほどの歓声が上がり、会場が揺れに揺れまくったことは言うまでもない。
今更話すことでもないが、兎にも角にもウェンディと呼ばれる民族はそのお上品な容姿に反して、とんでもない声量を誇るVeautiful Monsterなのだ。
まだメンバーがステージから捌けきっていないのにも関わらず、貪欲に湧いたアンコールの声。
これだけ精神も体力も消耗するショーを目の当たりにしながら、なんという求愛だろう。
その大歓声に引き寄せられるがまま、再びステージへ戻ってきた彼らの表情には文字でも写真でも映像でも再現しきれない童心が宿っていた。
超濃厚な本編への達成感が隠し切れないその最高の笑顔はまるで少年!
本日初のMCも早々に切り上げ、「赤い目で見つめないでくださいよぉ~ぅ!だーかーらー黄色い目で見つめないでくださいって~!」と、先輩にいびられるお調子者の野球部員のような口調でウェンディをおちょくった久我新悟のコミカルな煽りを合図に世紀のお祭り男『三原色ダダ』が恵比寿に参上!
作曲者である小林孝聡の雄叫びコーラスと制御不能なハイテンション煽り(何を言っているのか聞き取り不能!)が会場の熱をブチあげていく。
4人の選ばれし変態たちによる超常的な妄想と空想を見事に現象化させた快楽ダダもれタイムのアレソレは文字にするだけ馬鹿らしい騒々しさ。
悪戯青年久我新悟の「隣の芝生」役を買って出た好青年新井崇之の潔さも微笑ましかったが、そんな彼が最後の最後で見せた現役ヤンキーも真っ青な『SEX PUPPET ROCK’N’DOLL』の血気マックスタイトルコールがマァ凄まじかった。
あの雄全開の叫びにこの日のウェンディが燃え上がらないわけもなく、ステージと客席の境界線が完全に排除されたリキッドルームは文字通りカオス!
楽曲の端の端に至るまで熱を灯す彼らのパフォーマンスに曲の終わりを待たずして湧いた大きな拍手。
こんなにも色とりどりな芸術にしてやられた我々だったが、この日の最後に浮かべた表情はとても無垢なたった一色の笑顔であった。
止まない求愛の声がいつまでも響き渡るなか、史上最愛のアルトラショー『VLACK APRIL#2』は幕を閉じた。
VLACKに漂白された我々を待ち構える未来。
今夏のリリースが発表されたNew Single『陽気なノワール』、ついにホール公演にまで到達した進藤渉バースデーショー『nude』、そして毎年恒例のセレブな船上ライヴ。
「次の約束がある」というこれ以上ない幸せを嚙み締めながら、LIPHLICHとウェンディの共謀はまだまだ続く──