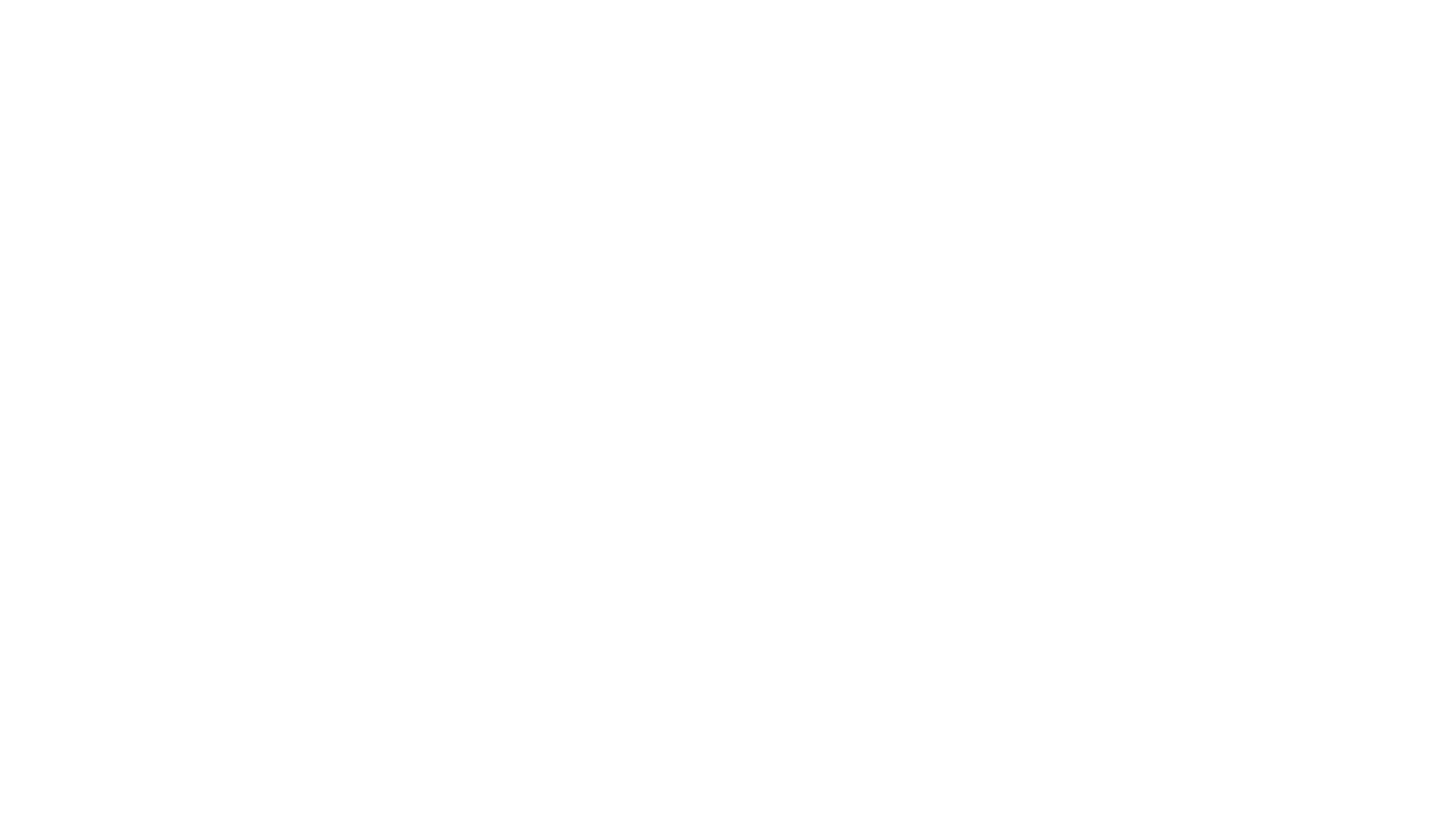今回ご紹介するのは「耽美を装う獣」として恐れられしMoranの『Eclipse』。
現メンバーでのファーストリリースとなる本作は、新体制のご挨拶におよそ似つかわしくない無礼講っぷりを炸裂させた意欲作でございます。
表題曲『Eclipse』は、相手を強く想うが故に少しずつ我を失っていく男の幸福と苦悩を描いた一曲。
この身の中で水嵩を増し続ける「相手の存在価値」とそれに押し潰されそうな「自我」との間を行き交う愛情の推移。
それをある種、ゲームの様に揶揄した詩から楽曲は幕を開けます。
とはいえ、主人公は開始早々ゲームオーバー一歩手前。
というのも、可細く弱弱しい存在へ与えているはずの愛情がいつしか自発的なものではなく、我の身から奪われてしまっている様な錯覚に彼は陥ってしまうのです。
「いずれは、相手にすべてを奪われてしまいかねない」
「この目に映る愛らしい仕草・言動もまた、そこへ到達させるための彼女の罠なのかもしれない」という猜疑心が終始彼を苦しめます。
幸福に溺れながら我を失っていくことへの耐えがたい不安と、それでも尚手放せずにいる唯一つの愛おしさ。
そこに漏れる主人公の『純度が増すたびに息が苦しくなる 余白ならとうに君が塗りつぶしてた』というもはや手遅れの嘆きは、その艶めく掠れ声も相まり、悩ましく官能的にさえ感じられる程の色気を漂わせます。
一見歪んでいる様に見えて、世に溢れる恋愛のほとんどは本来こういう在り方なのではないかと思わされるHitomiさんの詩・歌声の持つ説得力と、シリアスな詩世界とは裏腹に不埒な高揚を大いに煽るダイナミックなリズム。
その隙間をきらめきながら優雅に泳ぐ目がくらむほどの極彩サウンドは楽曲に宿る闇を無作為に照らします。
すがりつく細い腕を振り払うことも出来ず、押し寄せる悦楽と不信感に支配されていく人間の姿を主に天体学で用いる「浸食(Eclipse)」となぞらえる詩才に「ここの詩人は容姿才能共々衰えることを知らない!」と絶句するばかり。
お互いがお互いだけを必要とし、依存し、堕ちゆく快感。
過去、もしくは現在進行形で同じ境遇にある者にとっては、とても息苦しい作品となりますので、取扱にはくれぐれもご注意を。
そして、問題作といえば、カップリング曲『Vegaの花』につづく、初回盤のみに収録を許された『Vegaの花#2』を忘れてはなりません。
『Vegaの花』の中では描き切れなかった物語の細やかな心理・情景描写・息遣いをヴォーカリストとしてではなく、物悲しいピアノとストリングスの音色を纏う一人の語り部として表現に徹した、素晴らしき異端作に是非触れていただきたいのです。
舞台は、生まれつき病弱な少女にとってただひとつの「世界」であった10m四方の真っ白な病室。
そこへある日、足に怪我を負った少年が迷い込んでくることから物語は動き出します。
少年は、その無機質な病室で目にしたある物に強く心を惹かれました。
それは、壁に飾られた一枚の絵画。
描かれていたのは、「この世の果て」に咲くといわれているVegaの花。
この花こそが作品の象徴であり、全ての元凶でもあるのです。
怪我を治し、少女の世界から姿を消した少年と、余熱の残る白い部屋で一人、彼との再会を望む少女。
二人の「ひとりきり」が歩むその後の未来は、敢えて並走させず、時間軸をズラして綴られます。
そこで露わになるいくつもの願い、誤解、その全てが待ち合わせるラストシーンの衝撃にはきっと誰もが息をのむことでしょう。
双方の孤独が辿り着く、決して報われない結末にさえハッピーエンドにも似た温もりを感じさせられてしまう摩訶不思議な作品です。
少年が想いを示すために彼女に与えたがったモノと、少女が彼に求めていたものは似て非なるものでした。
そして、その小さな誤解によって生じた大きなズレを修正出来ずにいる二人の姿を傍観させられる中で、私たちはいくつかの疑問に出逢います。
そもそも少年は、病室へ迷いこむまでに何をしていたのか。
Vegaの花が咲く場所を「この世の果て」と名付けることになった理由は何だったのか。
悲劇の始まりと終わりを背中合わせに存在させることで延々ループしていく物語のトリックに悩まされながら、この作品が抱える十分すぎるほどの余白に聴き手自身が思い思いの空想を塗り足すというのもまた素敵なものです。
この作品にもし「サビ」を見出すのであれば、それは再生を終えた後に残る膨大な余韻なのかもしれません。
与えられるだけが能ではない、感性豊かな心をお持ちのお嬢様に最適な一枚。
語り尽くせぬ魅力は悪魔の如し。
嗚呼語り足らず。
もうちょっと文字のスペースが欲しかったなぁ。