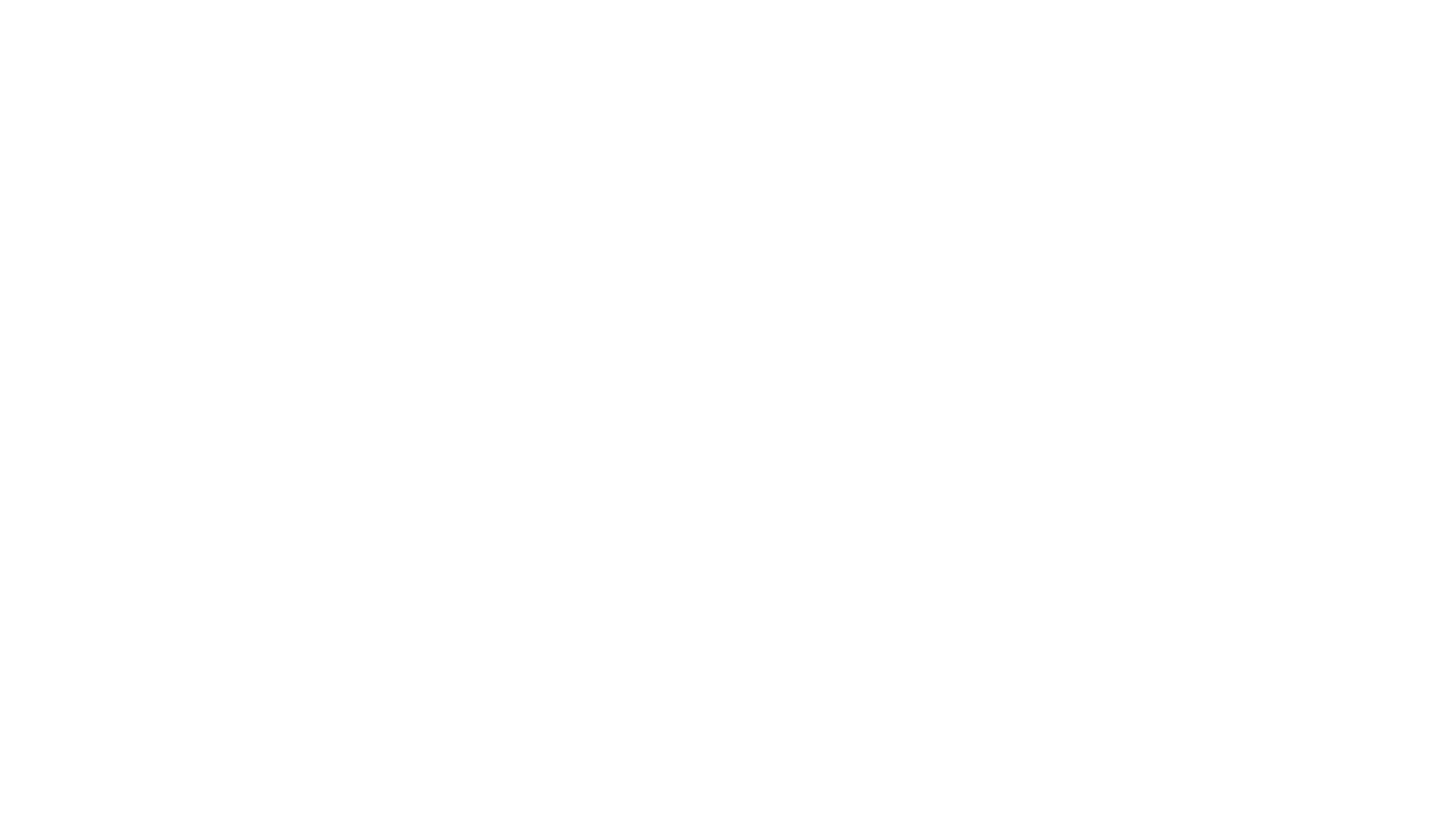その昔、今は亡き祖母が偏食家の私へ口癖の様に申しておりました。
「料理は一に食材、二に器、三四がなくて、五に食い手!(怒)」と。
どんなに素晴らしい料理と食器を用意したところで、口にする者の舌が馬鹿ならすべて台無しなんじゃい!という意味らしいのですが、これはなにも食に限った話ではなく、音楽をはじめとする全ての芸術に当てはまることだと思うのです。
今回ご紹介するLIPHLICHもまた、一人でも多くの音グルメ様に御試食いただきたいバンドのひとつ。
「奇才」「天才」その類の称号に憧れる者であれば、出逢った瞬間にハンケチを噛みながら嫉妬に身を揺らすことになるであろうVo.久我新悟さんの才。
彼の描く世界は、音を伝って聴覚からぐるぐると脳へと上り、眼で見るよりも遥かに鮮明な情景を聴き手の内側へ投影してしまう罪深き仕様。
「オリジナリティー」という言葉そのものの個性のなさを痛感させられる非常に厄介な作品揃いでございます。
人間の淀んだ部分をときに艶っぽく、ときにド皮肉に抉る感性。
怖いもの見たさの好奇心を異常なまでに刺激するこの音楽性を形容する言葉が見つからず、ついには「くがくがしい」という造語を使わざるを得ない状況にまでCD屋を陥らせるのですから世も末涼子。
そんな名脚本家率いるLIPHLICHにとって2枚目となるフルアルバムがコチラの『フルコースは逆さから』。
タイトルからして早々に捻れているこの作品が世に媚びたものでないことを真っ先に証明するのが洗礼的前菜『飽聴のデリカテッセン』です。
「評論家気取りのリスナー」と「作り手」との歪んだ関係性をレストランに現れる「舌の肥えた客」と「料理人」に代入し、そこに発生する致死量の皮肉を薄ーーーいオブラートに包んで蒸しあげた痛快極まる御唄。
少々皮肉の角が過ぎるせいで皮が破れ、中身が全て溢れだしてしまっている様にも見えますが、お気になさらず。
腹は満たされることを知っても耳は決してそうではない様で、放りこめば放りこむほど味わい深く、隙ありゃ果てなく欲してしまうもの。
そんな「人の欲」の有り様を艶めいたラブソングへと昇華させた5番目の刺客『VESSEL』。
「人間の”心”は、蜂の巣の様な形をした”器”である」という久我さんの独創的な定義の上に描かれた哲学は、あまりにも無情なものでした。
人から人へ注がれる愛に例え偽りがなくとも、受け手の器には無数の穴が空いている為にそれは絶えず流れ出てしまう。
永続的なその虚しい営みの中で脳裏にチラつきだす『(穴を)埋めるのは純粋な愛ではなく、理想の中に混じった不純物かもしれない』という推測に苦悩しながらも、そこには「例えそうであっても、せめて器が渇かない様に」と絶えず想いを注ぎ続ける男の姿がありました。
その愛に混ざる「嘘と欲と不安」を「不純物」と揶揄し、願った形とはまるで異なる理由によって塞がりゆく穴のひとつひとつに快楽とも絶望とも言い得ぬ感情を抱いてしまうという悪夢の様な愛の歌。
街に流れるラブなソングとは別ベクトル過ぎて、これまたどこまでもくがくがしい一品に仕上がっているのです。
はいカット!
上記は、過去にとある冊子のレビューコーナーで『フルコースは逆さから』を紹介した際に私が書いた文章の一部です。
あのコーナーはあくまでも「そのバンドをよく知らない方」へ宛てたものでしたので、とにかく「前向きで読みやすいもの」を念頭に置いて、文章の作成をしておりました。
そんな考えもあれば、文字数の関係もあって、この歌に潜むダークサイドの警告をバッサバッサとカットしなければならなかった経緯があり、「ここは残したいんだけどな…」などと一人こぼしながら、真夜中に真っ赤な眼でDeleteキーを連打した思い出が今でも鮮明に蘇ります。
でも、です。
幸か不幸かこの「ブログ」というツールには、書いても書いても引っ切り無しに現れる真っ白なスペースがあります。わんこそばみたいなもんで。
ですので、今日はあの日のウヤムヤを晴らすべく、心おきなく伸び伸びと初対面様度外視の文章を書かせてもらいます。
LIPHLICHの作品において、あまり類を見ない一対一の直接的なラブソングとなった『VESSEL』。
私は、この歌に作詞者である久我さんの「歪な愛情の根っこ」を見ました。
この楽曲に限ったことではありませんが、一昔前の彼はいつも何を「得る」ではなく、結果的に何かを「失う」人間の姿ばかりを描いていました。
でも、だからこそ不思議なのです。
どうしてこんな境遇の連続にあっても尚、彼の描く主人公は自信家揃いなのだろうか。
どうしてこうもこやつらは損得で愛情を測ろうとするのか。
どうして過去の失敗から学習をしないのか。
その答えをチラッと明かしてくれたのがこの名バラード『VESSEL』だったのです。
まずは、ヒトの満ち欠けのお話でも。
私たち人間は、例えば携帯の充電でもガソリンの給油でも「器に満ち満ちと原動力を溜めること」に安心感を覚え、その状態を確認して初めて「満たされている」ことを実感します。
しかし、こと人間の「感情」に関していえば、残念ながら互いの心に目盛りなどありませんので、相手の表情や態度、言動をもとに推測で好意の嵩を測らなければならず、相手が自分を、または自分が相手をどれだけ満たせているかなんていうことを正確に判断する術を持ち合わせておりません。
その曖昧さに救われる人もいれば、不安に押し潰されてしまう人もいる。
私得意の偏見ではありますが、久我さんは限りなく後者側の人間だと思うのです。
一般的なラブソングは、例えそれが結ばれない恋であったとしても、「好き」という感情が変わらず主人公の胸に宿っており、「だからこそ苦しい!忘れたい!でも忘れられない!サノバビッチ!」といった類の憂いを嘆いたものが大多数。
そういった歌に立つ主人公は一見不幸である様にもとられますが、「変わらぬ想いを抱き続けられる」という点においては、「とても贅沢な恋をした幸せ者である」という捉え方もできます。
しかし、久我さん家のベッセル君(多分長男)は、そこからして大きく違います。
というのも、この歌には節度を保った優雅なメロディーにはおよそ不釣り合いな非普遍的な愛がのさばっているのです。
「その穴から流れてしまうものだとしても、君に愛を注ぎ続ける」という決意が灯す紳士的な包容力ときたら、それはもう「トレビアン」の一言。
ただ、その優しさは”ある条件”を満たして初めて成立する感情だということを忘れてはなりません。
その条件とは、「彼女が彼からの愛を求めていたら」という点です。
そうであれば、これは必然的な「美しい相思相愛の歌」と成り得ます。
あの日に書いた記事では、あくまでも「拒まれてはいない」という前提で、作品の紹介を致しました。
では、あの女性が彼からの愛情を一切求めていなかったとしたら、この歌はどんな表情を見せるのか。今回はそこに踏み込んでみたいのです。
もし。
自身が愛されていないことに気付いていながらも決してその事実を認めようとはせず、「この愛情表現がいつか彼女に理解され、いずれ実を結ぶはずだ」と信じてやまない彼がいたとして。
もし。
「蜂の巣のような形をしている”彼女の心の器”」
それがもし、望んでいない愛情に満たされない様、彼女が故意的に空けた穴だったとして。
彼は、彼女が確かに示してみせた拒否反応にさえ、都合の良い理由をつけることでしょう。
例えば、こんな風に。
何気なく誰かを悪く言うのは 割と簡単な事だし
律儀に返ってくる痛みにもう 慣れてしまったかもしれない
この悪く言われる『誰か』というのは、おそらく彼自身のこと。
敢えて「かもしれない」と、そう濁すことで必要とされていない事実から目を背ける。
惜しみなく与えた愛情を欠片も返してもらえないどころか、一向に縮まることのない距離に一抹の不安を抱きつづける彼の心は次第に麻痺し、いつしか「傷つかない振り」を続けることにさえ慣れてしまったのでしょう。
こちらの好意を見て見ぬ振りするわけではなく、その都度律儀に牙を剥く彼女の言葉にさえ胸を痛めることが出来なくなってしまった彼の姿は、彼女にとってもはやヒトの形をした別の生き物に見えていたのかもしれません。
そうして善悪の分別が少しずつ虚ろになっていく彼は、それでもその重い頭で報われない自分自身を慰めます。
言葉は君にとってシガーの先につけた火で
ほんの少し時がたてば消えて後は灰になるだけだから
「君の云う冷たい言葉は、いわば瞬間的な気の迷いから発せられるものだから、それにわざわざ気を病む必要はない」と、きっと彼女からすれば一番に気付いてほしい敵意をいつまでも受け入れようとはしない。
しかし、少しずつ蓄積されゆく不信感に解れたその場しのぎの言い訳劇がそう長く続くわけもなく、虚しく愛を注ぎ続けるだけの彼は、この緩やかな旋律上で静かに狂い始めていきます。
久我さんが描く「自信家の失敗」によく見られる「こんなはずがないだろう」という困惑と焦りが彼の脳を更に歪めるのです。
時の流れとともに1つ1つと増えて行った洞穴
埋めるのは時じゃなく理想の中の不純物かもしれない
宛てがう愛に たまに混じった嘘と欲と不安が
少し詰まって ほらまた1つ ふさがったね
こうして、報われない想いへの苛立ちから芽生えた”支配欲”が顔を出し始める。
いつまでも繋がることのない想いを嘲笑うかの様、無情に過ぎてゆく時間。
その経過と共に一つまた一つと増えていく器の穴。
液状の愛は、そこに留まる術を失うばかり。
「せめて渇かない様に」と注ぎ続けた膨大な愛情が、まるで意味を成さないものであるという事実を突きつけられた今、彼は最愛の器に空いた無数の穴を「埋めてしまいたい」衝動に駆られるのです。
その「穴を埋める」という行為。
私の印象として、それは彼女を満たすというより、窒息状態へ陥れるイメージに近いものがあり、そこには愛情とまるで異なった「復讐心」さえ感じてしまいます。
とめどなく流れ続ける鮮麗な「純愛」は粘度が低く、穴をさらりとすり抜けてしまう。
だからこそ、「このままで構わない」という”嘘”と「このまま必要とされないのかもしれない」という”不安”を混ぜた高粘度の偏愛を注ぎつづける。
本来は「相手を満たすため」であったはずの行為が、いつしか「自己を満たすため」のものへと変貌を遂げたとき、「それもまた愛である」と許容する人もいれば、「それは違う」と首を振る方もいることでしょう。
いずれにせよ、「この愛が偽りであっても構わない」という彼の独りよがりな思想は、受け手である彼女からすれば恐怖でしかないことに変わりないのですが…
『少し詰まって ほらまた1つ ふさがったね』という会話の様な独り言には、ニタッと上がった口角が映ります。
ずっと探し求めていた「彼女の穴を塞ぐ方法」がこんなにも醜い手段であったことへの失望と、それでもこの手によってその穴が確かに埋まっていく快感。
渦を巻くように混ざり合った二つの相対する感情に揺れる”哀”とも”悦”ともとれる彼の口調。
それを再現する久我さんの歌声は大変美しいものです。
重ねる度、僅かに変化していくサビの詩。
そこにも彼の感情の推移が記されていました。
宛がう愛が 蜂の巣のような 君という容れ物から
流れていくのを ふせぐにはこの手じゃ足りない
宛がう愛が 蜂の巣のような 君という容れ物から
流れていくけど 今はもう少し 好きにさせて
今は流れてしまうものでも ずっと注いでいるよ
いつか満ちるまで
ひとり誓ったこの決意が彼女に望まれていないものであることに気付きながらも、この行為が決して過ちではないと信じていた。
しかし、その想いは彼女の強い拒絶によりいとも容易く絶たれ、それが叶わないものだと知った今、本来の願いであった「愛し合う二人」の理想さえも美しく思えなくなってしまう。
そうまで理解しても尚『今はもう少し好きにさせて』と縋る彼の歪んだ求愛に恐怖以上の切なさを覚えてしまう理由は、やはりLIPHLICHというバンドに宿る魔力に他なりません。
文字では到底伝えきれない程の心労が滲み、その声を通して今にも溺れてしまいそうな男の悲哀と憂鬱が聴き手の喉に手をかける。
こういった人間の憔悴と行き場をなくした「感情の泣き声」を表現させたら久我さんの右に出る者はいないと、彼の左に立つ新井さんもきっとそう思われていることでしょう。
この歌は、久我さんの得意とする「叶わなかった理想のかたち」を描いた作品でありながら、彼の伝家の宝刀でもある「苦し紛れの捨て台詞」が最後まで姿を現しません。
他の楽曲とは比べ物にならない程の落胆と失望に破れた精神に余力などあるはずもなく、歌の上で弱弱しく横たわる男の姿がただただ聴き手の脳裏に浮かぶまでです。
冒頭で歌われる
あれから動けない本当の理由 お気に入りの靴を無くしたから?
裸足で行けるほど子供じゃない そう言う君は裸足が好き
どこか親心の様な目線で彼女に問いかけるこの一節もまた、今となってはその場に留まる他ない哀れな彼の影をそのまま映しているかの様。
このやりとりからも察せられるように「理解者であるつもりの男」と「理解されたがらない女」は、永遠に交わることがないのです。
猫目の伯爵をはじめとする「無礼なキャラクター」の皮を被ったときは、憎らしい程に自信家で饒舌だったはずの彼が、生身の人間同士の恋愛を歌おうとした途端、まるで別人かの様に臆病になる。
そういえば、彼らの歌にはもう一人似たような登場人物がいましたね。
あれは確か『piropo』という歌に生きた女の子でした。
意中の男性に焦がれて仕方ない彼女の恋心をくり抜いたキュートなラブソング。
主人公の性別こそ違えど、この歌の彼女もまた『VESSEL』の彼と似た考えの持ち主に思えます。
その証拠といってはなんですが、可愛らしい猫撫で声で手ぐすねをひいたピロポちゃん(多分末っ子)の台詞をお聞きください。
その目で満ちない私の 純真を見抜いて
勝手にその気になったの とりあえずは気付いて
これは、『VESSEL』でいうところの『今はもう少し好きにさせて』とそう遠くない意味を持つ言葉で、「あなたが私に興味ないことなど百も承知。それを自覚した上での恋なんだから、勝手に好きでいることは罪じゃないはずでしょ?」という、被害者からすれば鳥肌モンの理論です。
この自己中っぷりは、好き放題に他人を悪く言った直後に「まぁ悪い子じゃないんだけどね」と言葉を足すことで、それまでの全てをマイルドにしようとする性悪女にも近しいものを感じるわ。
今ではもう手に入らなくなってしまった2nd FULL ALBUM『フルコースは逆さから』ですが、ウェンディのお嬢様は世話好きな気質ですので、「聴きたいなぁ」と思われた方は最寄りのウェンディ事務局まで声を掛けてみてはいかがでしょう。
私でよければいつでも御貸ししますので、さいたま市内で見掛けた際には肩を叩いてください。一応振り向きます。
長々と失礼致しました。
それでは皆様よい令和を。